
自治体でのペットの災害対策とは?
豆知識
今まで4回にわたり、飼い主の役割と自治体の役割についてお話してきました。では、実際に自治体では、平常時にどのような対策をしているのでしょうか?いざ災害が発生してからでは、冷静な行動が取れないかもしれません。大切なのは、正しい知識を持っておくこと。各自治体での対策を知り、災害に備えておきましょう。
1. 人とペットの災害対策に関する飼い主等への
普及啓発・避難訓練
 犬や猫がペットとして飼われている頭数は、おおむね2,000万頭弱と言われています。しかし、ペットの飼養に関する正しい知識やペットのしつけが十分でない飼い主もいるのが現状で、災害時のペットとの同行避難や避難所での適切な飼養が難しい場合があります。また、迷子札やマイクロチップなどの所有者明示が不十分だと、行方不明になったペットが保護されても、飼い主の元に戻れる確率がかなり低くなってしまいます。
犬や猫がペットとして飼われている頭数は、おおむね2,000万頭弱と言われています。しかし、ペットの飼養に関する正しい知識やペットのしつけが十分でない飼い主もいるのが現状で、災害時のペットとの同行避難や避難所での適切な飼養が難しい場合があります。また、迷子札やマイクロチップなどの所有者明示が不十分だと、行方不明になったペットが保護されても、飼い主の元に戻れる確率がかなり低くなってしまいます。
そのため、自治体は動物愛護推進員や関係団体・機関と連携して、災害時にもペットが社会に受け入れられるよう、ペットの災害対策の意義を普及しています。平常時から行うべき対策や災害時の行動について、飼い主等に対し指導、普及啓発を行い、必要に応じて避難訓練なども実施しています。
2. 避難所や応急仮設住宅でのペットの受入れ対策
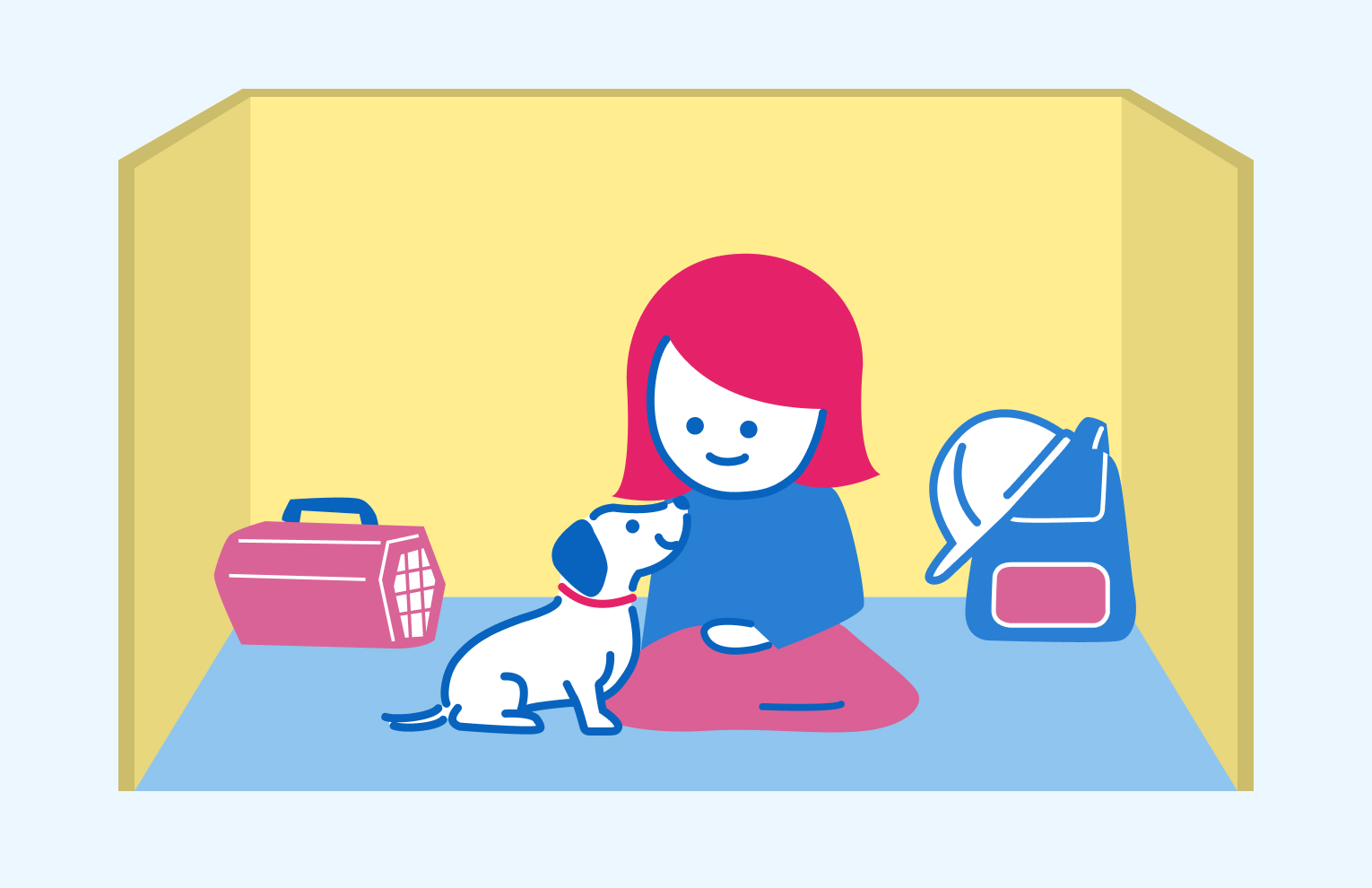 自治体にもよりますが、飼い主がペットと同行避難することを前提に、指定避難所での受け入れや応急仮設住宅でのペットとの同居などについて、体制を整備しているところが多くあります。災害時でも飼い主が避難所や応急仮設住宅で、適正な飼養管理ができる体制を検討されていますので、地域防災計画へのペットの受入れに関する記載などを、お住まいの自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
自治体にもよりますが、飼い主がペットと同行避難することを前提に、指定避難所での受け入れや応急仮設住宅でのペットとの同居などについて、体制を整備しているところが多くあります。災害時でも飼い主が避難所や応急仮設住宅で、適正な飼養管理ができる体制を検討されていますので、地域防災計画へのペットの受入れに関する記載などを、お住まいの自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
■指定避難所でのペットの同行避難者の受入れ
自治体が整備した指定避難所では、ペットの飼養場所や飼養管理のルールが定められてる場合があります。ペットに起因した避難者からの苦情やトラブルを削減するためにも、あらかじめ近くの避難所のルールなどを確認しておきましょう。また、避難所によっては、誰もがすぐに利用できる簡潔な指示書(スターターキットなど)が整備されていることもあるので、必要に応じて問い合わせなどを行っておくのも良いかもしれません。
指定避難所は、動物が苦手な人や動物アレルギーを持っている人など、様々な人が共同生活を送る場所です。ペットの鳴き声や毛の飛び散り、臭いなどへの配慮が必要になります。特にペットとの同伴避難や同室避難では、多様な人と関わることが予想されますので、日頃からペットのしつけをしておくことが重要です。
3. 必要な物資の備蓄・更新
 自治体が設置している動物愛護センターや保健所などでは、ペットフードなどの備蓄品が用意されています。備蓄品や救援物資は、避難所などで支援が必要なところに配布するほか、在庫の管理もしています。
自治体が設置している動物愛護センターや保健所などでは、ペットフードなどの備蓄品が用意されています。備蓄品や救援物資は、避難所などで支援が必要なところに配布するほか、在庫の管理もしています。
ただし、避難の長期化などによって物資が不足することも考えられるため、自分とペットの物資については、飼い主自身が平常時から用意しておくことが非常に大切になります。
以上のように、自治体ではペット避難の対策を立てているところも多くあります。特に災害に直面した経験のある自治体では、対策内容が手厚くなっている場合もあります。しかしながら、あくまで災害対策は「自助」が基本です。自分とペットの命を守るために、お住まいの自治体の対策を確認しておくとともに、避難訓練などにも参加し、災害時に慌てないように準備をしっかりとしておきましょう。
下記に、文中でも登場したスターターキットについての詳細や、自治体の災害対策の一例を紹介しますので、併せてお読みいただければと思います。
-
避難支援ツールの一例
スターターキット (ファーストミッションボックス)
災害が発生した直後の現場(避難所や対策本部など)には、必ずしも担当者や運営マニュアルを熟知した人がいるとは限りません。
この対策として、最初にそこに到着した人やその場にいあわせた人が、速やかに体制が整えられるよう、「最初にやるべきこと)」が記載されたスターターキット(ファーストミッションボックスとも呼ばれる)を備える取り組みが始められています。
■スターターキット(ファーストミッションボックス)の目的や特徴
1)初期の対応に使用するものである
2)イラストなどとともに、誰が読んでも理解できる指示が、1項目ずつ簡潔に記載されている
・カード形式では 1カードに1ミッション ・チェックリスト形式では1項目に1ミッション
3)その場にいる人が指示されたミッションを1つずつ実施していくことで、手順に従った業務が遂行できる
4)避難所の立ち上げ、集合住宅での避難誘導、災害対策本部の設置など、様々な状況に応じたパターンがある
5)1人で同時に対応できない役割を複数抱え込むことがないように、その場にいる人に協力を求めて作業を分担できるように組み立てる
-

普及啓発の方法(ハンドブック)
香川県・高松市
■ハンドブック「あなたとペットの災害対策ハンドブック」
香川県と高松市では、「あなたとペットの災害対策ハンドブック」を作成して、ペットの災害対策の普及啓発に努めています。
参照はこちら
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/6081/ssmaqc181018120910_f17_1.pdf -

民間団体との連携
宮城県・石巻市
■石巻市社会福祉協議会とボランティアチームが「犬との幸せ講座」を開催
石巻市社会福祉協議会と(一社)日本ペットサロン協会の会員有志によって、平成28年2月から「犬との幸せ講座」が開かれています。
これは、平成23年の東日本大震災の際に、緊急災害時動物救援本部(現在のペット災対協)が企画し、応急仮設住宅でペットを連れた被災者への支援として(一社)「日本ペットサロン協会」が実施した、被災ペットのトリミングなどによる衛生管理サービス事業がきっかけになりました。
平成29年11月25日に行われた第3回目の企画では、ペットのしつけや疾病への対応とともに、同行避難が重要なことなど、災害時の行動として大切なことがペットを連れた参加者に伝えられました。
災害への取り組みでは、特に支援ボランティアの関係などで、各地の社会福祉協議会との協働が重要なことから、各地でこのような取り組みが進むことが期待されています。
-

平常における物資の確保の例
福島県 (平成23年 東日本大震災)
平成18年度から動物の救護に必要な物資の備蓄を行い、県内5箇所の保健所に分散して保理し、災害発生時に、被災地に配布する体制を整えていました。備蓄していた品目と数量は以下の通りです。
・ペットフード
ドッグフード 500kg
キャットフード 125kg・ケージ 50台(大 25 / 小 25)
・餌入れ、水入れ 50本(大 25 / 小 25)
・首輪 50本(細 25 / 太 25)
・係留用チェーン 50本(細 25 / 太 25)
・動物保護用麻酔薬
セラクタール 500ml
ドミトール 150ml
アンチセダン 150ml・薬浴用水槽 5(500リットル)
-
出典
-
「人とペットの災害対策ガイドライン」(環境省) P.52-75
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002/0-full.pdf
【自治体等が行う人とペットの災害対策(平常時)】を加工して作成
-





