
災害が起こった時、自治体には頼れる? ②災害時のペット対策
豆知識
前回、発災直後に自治体が行う初期対応について解説しました。では、災害発生2日目以降から平常時に戻るまで、実生活で自治体の支援はどのようなものがあるでしょうか。詳しく見ていきたいと思います。
災害時のペット対策 (2日目以降の緊急対応)
(1)ペットに関する情報窓口の一元化

自治体や現地動物救護本部等は、災害時のペット対策に関連する問い合わせを受ける相談窓口を設置し、情報収集と発信を一元化するよう整備を進めていることがほとんどです。この窓口は、自治体の動物愛護センター等の他、地方獣医師会が現地動物救護本部等の事務局である場合は、地方獣医師会に置かれていることも考えられますので、早めに情報収集を行うことが重要です。
相談窓口では、各避難所でのペット同行避難者の避難状況や在宅避難者の状況、それぞれの避難先でどの様な支援が求められているのかなどについて正確な情報が集められている他、自治体などによる支援内容や指定避難所における飼養方法の指導、ペットの一時預け先などの情報の提供を行っています。確定した情報はウェブサイトなどを通じて発信されますので、そちらもチェックするようにしましょう。
(2)保護が必要な動物への対応

災害時にはペットが怪我をしたり、ペットとはぐれてしまったりということも考えられます。また、ペットを飼っていない人でも、負傷した動物を発見することもあるでしょう。そういった場合には、すみやかにお住まいの自治体へ連絡を取ってください。また、ペットと一緒に避難ができない時には、自治体が飼い主からの一時的な預かりを実施していることもあるため、必ず相談するようにしてください。
(3)避難生活での飼い主支援
■ 物資の支援

避難生活が長くなると、持参してきたペットフードなどだけでは物資が不足してしまいます。自治体などでは、指定避難所への定期的な巡回や、避難所の管理者等からの定期的な情報収集を通じて、各避難所で必要な救援物資を把握して、その確保に努めています。物資が得られずに困った時には、まずは相談してみましょう。
■ 飼養環境整備のための支援
ペットと一緒に避難するためには、避難所が整備されているかが重要です。自治体によって同室避難、同行避難ができる体制を整えているところもあれば、一時預かりなどで対応しているところなど様々です。自己判断で避難を行わず、対応については自治体の体制を必ず確認するようにしてください。
【避難所で受け入れがある場合】

- ペットとの同居または住み分けなどについては、各避難所のルールに従い、ペットの世話は飼い主が自ら行う。
- 鳴き声、臭い、毛の飛散、糞尿の処理など、避難所でのペットの飼養に起因した苦情やトラブルがなるべく起こらないよう、平常時からしつけを徹底しておく。
- 飼養ルールや衛生管理の方法などについては飼い主が相互に協力し、飼養スペースの衛生管理や、ペットを適正に飼養するように努める。
※障害のある方が同伴する身体障害者補助犬(「身体障害者補助犬法」で定義される盲導犬、 介助犬及び聴導犬)はペットではなく、要支援者の支援として考えられていますので、自治体にお申し入れください。
【車や在宅で避難をする場合】

- 支援物資や情報を入手するために、必要に応じて指定避難所などへ足を運ぶ。
- 飼い主が避難所に避難し、ペットを自宅で飼養する場合は、避難所から自宅に世話をしに通う方法もある。ただし、二次災害の危険がある場合はこの方法は避け、自治体に相談する。
- 車の場合は、ペットだけを車に残さない。
- エコノミークラス症候群や熱中症に注意する。
やむを得ず、一時預かりを要請する場合も、自治体を通して相談するとスムーズです。預け先は、動物救護施設、動物病院、動物愛護団体及び個人ボランティア宅での預かりなど、状況に応じて異なります。
(4)動物由来感染症の予防

避難所では様々な人が生活をしています。ペットを飼っている人は平常時からペットの健康管理に注意し、予防接種を実施するとともにノミなどの外部寄生虫を駆除し、トリミングなどをすることで健康や衛生を確保する必要があります。健康や衛生が確保されていないペットは、感染症対策などの観点から、指定避難所や応急仮設住宅、動物救護施設や一時預け先などでの受入れが出来ない可能性があるので、日頃からペットの衛生管理をしておきましょう。
また、避難時には通常時と違う環境(指定避難所、応急仮設住宅、動物救護施設、一時預け先など)でペットが生活することを考えると、免疫力が低下するとともに、他のペットとの接触が多くなるので、ペットの感染症のリスクが高まることにも留意する必要があります。
自治体では、獣医師の巡回診療の実施や、提携動物病院での診察を行っていますので、飼い主がペットの健康状態に異常を感じた際にはすぐに相談しましょう。
避難所はペットはもちろん、人もストレスにより免疫力が低下します。断水で手洗いが行えず、空調も機能しない中で、温熱環境も維持できずに衛生環境が悪化する懸念もあります。日常生活の中では問題のない接触でも、ストレスや恐怖によってペットが噛みついてしまったり、ひっかいてしまったりということも考えられますので、充分に注意して生活を行う必要があります。
(5)応急仮設住宅での飼い主支援
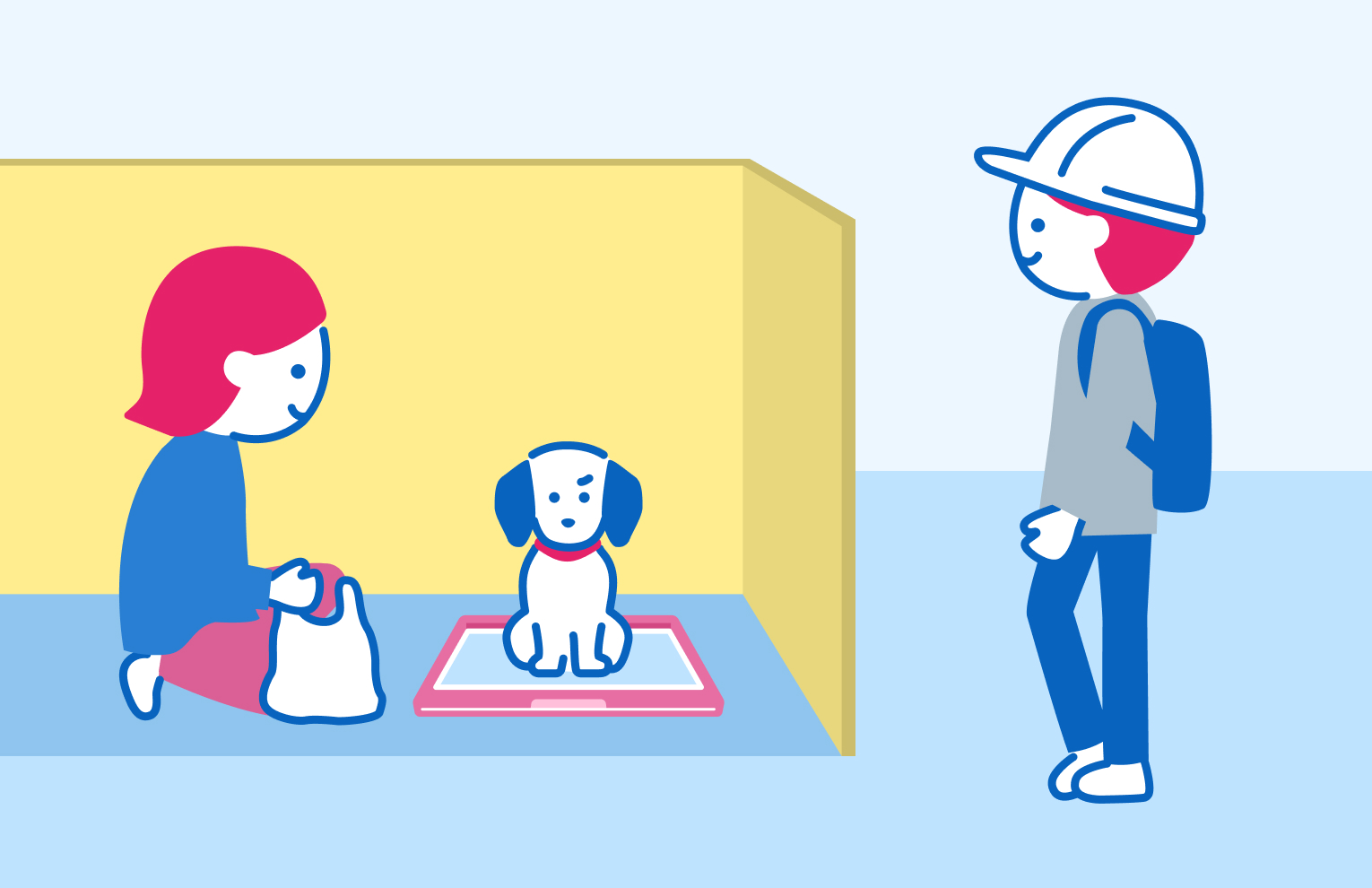
災害による被害が甚大で、自宅に戻ることができない場合、仮設住宅での生活を余儀なくされることもあります。その際、ペットと一緒に暮らせることは日常を取り戻すためにも大切なことですが、ペットを飼っていない人との距離が近い共同生活となるため、避難所と同様、相手への配慮が求められます。
そのため、応急仮設住宅の設置・管理者と現地動物救護本部などは、応急仮設住宅でのペット飼養のルール作りや、飼い主に対する適正な飼養指導・支援を実施しています。「原則として室内飼い」が推奨される可能性が高いため、大型犬や元々室外で飼育していたペットについては、別途自治体への相談が必要となります。状況によっては、ケージやサークルなどの貸出支援を行っていることもあります。ペットの適切な飼養のために「飼い主の会」などを立ち上げ、皆が心地よく暮らせるようにマナーを遵守することが大切です。
また自治体では、応急仮設住宅の入居期間を経て自立した生活再建に繋がるよう、 自立支援を基本とし、無料での物資やサービス、獣医療などの提供は段階的に減らし、応急仮設住宅を出た後も自らの力で継続して飼養できる環境作りへの協力も行っています。

いかがでしたでしょうか。被災することは考えたくはないですが、いざ起こってしまってからでは対策が間に合わないこともあります。災害にあたっては「自助」が基本とはいえ、緊急時こそ、様々な支援やサービスを活用して、できるだけ少ない被害で危機を乗り越えられるようにしたいですね。
自治体の取り組みについては、以下の記事も参考にしていただければと思います。
👉️りく・なつ防災コラム「自治体でのペットの災害対策とは?」
ご自身の自治体でのペットの防災対策や相談窓口については、こちらからお探しいただけます。
👉️りく・なつ防災コラム「全国ペット防災情報」
また、以下に過去の事例をおまとめしていますので、併せてご一読ください。
-

【環境省】各地の動物救護活動
特に地震の被害が多い日本では、発災時にどのように動物を救護できたのか、その被災概況をまとめ、次世代に活かしています。
各地での取り組み内容について、ぜひご一読ください。東日本大震災における被災動物救護活動
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2508c/02-1.pdf熊本地震におけるペットの被災概況
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3003/full.pdf -

【環境省】各地の被災ペット対策における対応事例・課題となった事例
実際にペットとの避難受け入れや、動物救護を行った自治体では、その事例や課題についてまとめています。自身が被災した時に困らないよう、平常時から行える対策の参考になります。
各地の被災ペット対策における対応事例・課題となった事例
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3003/06.pdf -

【仙台市】避難所対応事例
仙台市では、ペットの飼養数が多い地域で、「ペットの会」が自発的に発足した事例があります。飼い主からしつけ教室を開催して欲しいとの要望が有ったため、外から講師を呼び、しつけ教室を開催したのがきっかけとなりました。糞拾い運動も、始めはボランティアが実施していたが、飼い主がやるべきことと気づき、飼い主も拾うようになりました。
市では、飼養者向けに避難所での飼養ルールやペット情報カードを配布しており、オンラインでも閲覧ができます。
「ペット情報カード」と「明日来るかもしれない大災害に備えてペットのために準備すべき、7つのポイント!」
https://www.city.sendai.jp/dobutsu/kurashi/shizen/petto/hogodobutsu/aigo/dobutsu/documents/pet-card-7point.pdfまた、災害対策や連絡先についてもまとまったページがありますので、ぜひ参考にしてください。
https://www.city.sendai.jp/dobutsu/kurashi/shizen/petto/hogodobutsu/aigo/dobutsu/saigai.html
-
出典
-
「人とペットの災害対策ガイドライン」(環境省) P.84-114 【災害発生時の初期対応(発災当日~翌日)】を加工して作成
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002/0-full.pdf
-





